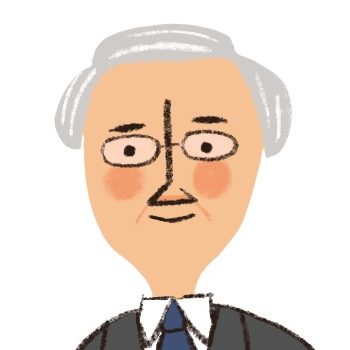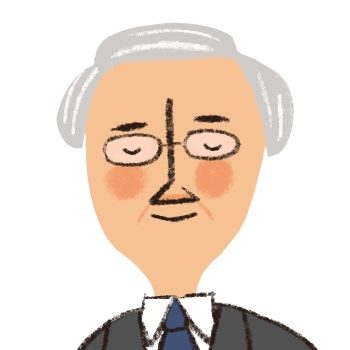4月18日 木曜日、晴れ。
いよいよ、旅の結び、鳥取県民藝美術館でのインタビュー。
フライパンで焼かれる直前のウインナーの心地。
好奇心がプリプリに膨らんで、皮がパチンと弾ける期待感。
思い出したら緊張して、例えまでヘンテコになる。
鳥取民藝美術館の前に到着しました…頑張るぞ…リラックスするぞ…#民藝旅 #鳥取県 #鳥取民藝美術館 pic.twitter.com/IU9tCAWlDo
— 東堂 優 / Yu TODO #民藝旅 (@todo_yu) April 18, 2019
東京の日本民藝館ともちがう、独特の建物。室内は少し暗い。
緊張して、のどがキュッと狭くなる。
約束の時間まで、館内をぐるぐる見てまわった。
 パン切り包丁、ゆみさんから教えていただいたあの、包丁の本物。
パン切り包丁、ゆみさんから教えていただいたあの、包丁の本物。
1階は、鳥取の民藝運動をリードした吉田璋也さんがプロデュースしたもの。
2階は、吉田さんの著書「民芸入門」で紹介された品の実物が展示してある。
10:30、鳥取民藝美術館 常務理事、木谷様へのインタビューが始まった。
(インタビュー内容は一部抜粋、編集しています。)
* * *
1. 民藝のはじまりと、鳥取のダヴィンチ吉田璋也
そして、柳たちが美しいと言っているものを民藝と呼ぼう、ということになり、「なぜ民藝は美しいのか」という民藝美論を展開していきました。
それで、色々とコレクションしてみると、柳の選んだ民藝品はだいたい江戸時代の中頃から、明治の中頃までのものが多かったのです。
しかし、それはあくまでも美術品なので、日用品としては使えません。
日常に使えるような値段で、(以前はなかった)陶器のコーヒーカップを作ったり、あるいは洋皿を作ったり。
そうやって、現代の生活で使えるものを作ろうということをプロデュースし始めました。昭和6年のことです。
ただ、作るだけではなくて、それを販売する組織も必要であるということで、「たくみ工芸店」、ショップを昭和7年に鳥取で作って、昭和8年に「銀座たくみ」を作るわけですね。
そう思うと、柳が考えていた民衆的な工藝の美しさが消費者の、一般市民の生活の中に入っていくわけです。そうすると、生活が美しくなる、ということが大切だと。生活が美しくなることで、民衆的な社会がよりよくなっていくんだと。「美による社会改革運動を自分たちはやっているんだ」と、いう信念なんですね。吉田璋也さんは。
ですから、「いまの民藝品はありえないのではないか」という疑問は、実はそうじゃなくて。
例えば牛ノ戸焼という焼物がありますけれども、そこの焼物はもともと、4種類しかないんです。黒と白と緑と茶色と。赤とか黄色とかカラフルな色を使って民藝品を作ろうっていうんじゃなくて、その窯の伝統に従ってコーヒーカップを作ってみたり、あるいはお皿を作ってみたり。現代の生活に合うものを新しいくデザインして作っていく、ということをした人が吉田璋也さんというわけです。

1. 柳宗悦が選んだもの
2. 柳宗悦の美学に沿って作られたもの
* * *
2. 柳宗悦が選んだ物でなくても、民藝品となるのか?
「この民藝館は今日の生活、明日の生活と深い関係を持たねばならない。私たちはここで私たちの信ずる個人作家の製作、および今なお健在する地方民藝への紹介に大きな使命を感じるものである。」#民藝四十年 #民藝旅
— 東堂 優 / Yu TODO #民藝旅 (@todo_yu) March 14, 2019
「だが私たちは、ただ古作品を陳列することに仕事を止めようとするのではない。(中略)もし美の問題を過去の歴史に止めるなら、それはただ愛玩的な鑑賞に止まってしまう。私達にとって大切なのは、むしろ新作品への準備である。」#民藝四十年 #民藝旅
— 東堂 優 / Yu TODO #民藝旅 (@todo_yu) March 14, 2019
日本民藝館に展示してあるようなものが美しいもの。でもそれは、生活のなかに取り入れられないでしょう?骨董品で、一個しかないでしょう?
つまりね、骨董品で飲むのもいいんですけど、それって1個しかないじゃないですか。壊れちゃったら、代わりもないし。第一、高価なものだし。美術品だし。壊れちゃったらその美術品の価値も失われるし。それに数もそんなにない。ということで、現代の生活に取り入れることはできない。で、それをそうじゃない。現代の生活に取り入れなくちゃいけないんだ、という信念のもとに、新作民藝運動を展開したのが、吉田璋也さんという人なわけです。
そして、戦後になると各地で新作民藝運動がはじまりました。ただ、戦前にはそういったものはなくって、新しい新作民藝っていうのは鳥取と、島根県が中心でした。
そういった意味で、種類の多さとか、規模の大きさとかいったら、他にないレベル。他を圧倒するわけですよ。
だからそういった意味で、吉田璋也の新作民藝運動っていうのは一番最初に起こったし、一番最初に成功したし、しかもデザインをするだけではなく、プロデュースや販売して言ったんです。資本を集めるとかね。
例えば、銀座のたくみだって、資本金はぜんぶ鳥取の人たちからお金を出して、銀座に出店したんですよ。
というのは、その当時の柳さんの思いとして、明治の中頃に全て廃れていったわけではなくて、まだ少し残っていたんですね。「残存民藝」という言い方をしますけれども。
残存民藝というものを、いま、売ることを考えてあげないと、生産が止まっちゃうわけです。しかも、その残存民藝というのは、まだお値段も安い、職人さんが作るしごとばっかしですから。
だから、それを全国流通にしないと生産が止まってしまう、という危機感が柳にはあって、誰かそういった店をやってくれるものはいないか。ということを、柳は東京で考えていたわけです。
吉田璋也さん…
ですから、戦前から建物の保存運動をするとかね、それから、自然保護だとか、景観を守るとか。こういったことをも昭和6年から始めているんですよね。
特に戦後になってから、日本が経済成長していくので、自然破壊、環境破壊、それから歴史的建造物の破壊、こういったことが進むんで、そういったことに関して警鐘を鳴らし、保存運動を自らもしていく、と言うことをやっていった人ですね。
単にプロデュースで民藝品をやるっていうより、なぜ民藝品を流通させようと考えたのか、生活の中に取り入れてもらおうと言うことを考えたのかということは、生活を美しくすることによって世の中は良くなるんんだ、という理念があるからです。

インタビューは、次回「民藝と工業デザイナー、鳥取 × フィンランド」へ続きます!
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
\SNSへのシェア、感想、とてもよろこびます/